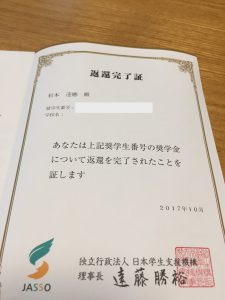この記事はpotariにも掲載しています。potariでは写真が掲載されています。
2020年1月、ドキュメンタリー映画『プリズン・サークル』の公開がはじまった。わたしはこの映画のクラウドファンディングの支援者であり、監督の知人でもある。つまりこの記事は、まったくの第三者による映画のレビューではなく、応援記事であることをおことわりしておく。
『プリズン・サークル』は、島根県の刑務所で唯一おこなわれている受刑者同士が対話する更生プログラムを描いたドキュメンタリー映画。犯罪者をどのように処遇すべきなのか、犯罪へいたる背景は何なのか、犯罪者は更生できるのか、見るものに多くのことが問いかけられる。同時に、自分の経験を振りかえり、ひいてはわたしたちの社会のあり方をも考えさせられる。
この記事では、映画の要素のひとつであるアニメーションを紹介したい。以下の内容は、公開初週に開催された、坂上香(監督)と若見ありさ(アニメーション監督)のアフタートークの内容をもとにしている。
『プリズン・サークル』は、ドキュメンタリーでありながら、はしばしにアニメーションが挿入されている。坂上は、アニメーションをとりいれた経緯を語った。法務省の判断で、登場する受刑者の顔が一切出せず、ぼかし処理せざるをえなかった(ぼかし処理だけで数か月かかったという)。もっとも伝えたい人間の表情を消されてしまい、ドキュメンタリーとして成立するのか危ぶまれた。その問題をのりこえるため、彼らが語る子ども時代のエピソードを、なんとかビジュアルで見せる方法を考えていたとのこと。そんななか、アニメーション作家の若見と出会って意気投合し、はじめて共同制作することになった。
坂上が編集したシーンにあわせて、若見が砂絵によるアニメーションを制作した。砂の絵は青みがかった色調とセピア調とがある。柔らかくやさしい絵のトーンと、暴力やいじめ、虐待、ネグレクトなどの体験を語る声にはギャップが大きく、最初はたじろいでしまう。
アニメーションの制作期間は、およそ2か月強という短期集中である。毎日9時間かけ、ガラス板にのせた砂粒をすこしずつ動かし1コマずつ撮影していく。もし制作中に、地震が起きたりして予期せず砂が動いてしまったら、シーンの最初からつくり直しだ。若見は、制作にあたって、虐待に関する書籍を読みまくり、受刑者が過ごしたであろう間取りのアパートの部屋を取材したという。柔らかなタッチからは、即興的につくっていたように感じられるが、じつは綿密なリサーチを経て作られていたのだ。
結果として、この映画のアニメーションはリアリティを補う添え物どころか、重要な要素になっている。映画の舞台は基本的に刑務所のなかだ。無機質な建造物を背景に、蛍光灯のあかり、プラスチック製の椅子など。どちらかといえば、のっぺりとした画がつづく。みな丸坊主の男性受刑者たちの顔や表情は隠され、彼らの感情をつかみきれない。そのなかではっとするのが、ときおり挿入される刑務所の各所と島根県浜田市の四季の風景。そして、アニメーションだ。
砂絵のアニメーションは、映像としての情報量がけっして豊富ではない。しかしその特性がかえって観客の想像をふくらませている。この映画のきびしく制限された映像に、アニメーションがイマジネーションの翼を与えているのだ。一粒の砂はだれかの涙のようだ。まだらに散らばる砂のかたまりは、恐怖に震える人の鳥肌のようでもある。あるときは、一粒一粒の砂が一人ひとりの人間に見えた。環にそってならぶ砂粒は、まるで受刑者たちがつくる人の輪、サークルのようだ。それに砂粒が動いているということは、それを動かすアニメーターがいるということでもある。砂絵を見ながら、アニメーターの存在や手触り、息づかいまで伝わってきた。
『プリズン・サークル』は上質なドキュメンタリーであり、すぐれたアニメーション作品でもある。あのアニメーションなくして、顔の見えない受刑者に感情移入できるだろうか。その答えは、ぜひ自分の目でたしかめてほしい。
最後に上映情報をお知らせ。九州では、KBCシネマ(福岡市)、シアターシエマ(佐賀市)、Denkikan(熊本市)で上映予定。劇場公開時でないとなかなか見ることができない映画になりそうなので、ぜひ劇場で。
『プリズン・サークル』公式サイト
https://prison-circle.com/